AwView 活用事例インタビュー
活用事例昭和女子大学 食健康科学部 健康デザイン学科 様

昭和女子大学 食健康科学部 健康デザイン学科(https://www.swu.ac.jp/faculty/health/kenko/)
昭和女子大学 食健康科学部 健康デザイン学科は、人体と栄養に関連する科学的基礎知識を学び、食・美・運動の3つの観点から「健康のスペシャリスト」をめざす学科です。今回は卒業発表のテーマとして、災害時での活用を見据えた野菜の乾燥方法の検討を行うために、AwViewでの水分活性測定を実施されたということで、指導された不破先生と、実際に水分活性を測定された4年生の柴田様にお話を伺いました。
※本内容は2025年2月時点の情報に基づいています。
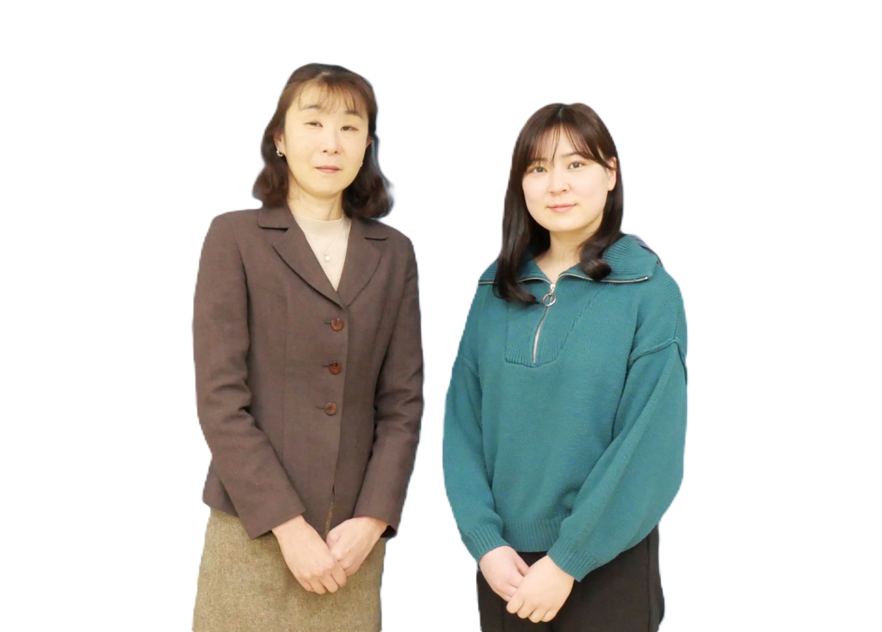
インタビューを受けてくださった方々
- 食健康科学部 健康デザイン学科 准教授 不破 眞佐子 様
- 食健康科学部 健康デザイン学科 4年生 柴田 真衣 様
不破先生のご専門分野について
ー まずは、不破先生のご専門の分野について、教えてください。
不破先生 : 給食経営管理を専門としており、そのなかでも栄養管理や衛生管理を中心的に取り組んでいます。昭和女子大学は栄養士養成施設なので栄養管理については、幅広いテーマに取り組んでいます。また衛生管理についても、給食は大量調理するなかで、絶対に食中毒を出してはいけないということが使命ですので、その点で重点的に関わっています。
ー 現在興味を持たれているテーマはありますか?
不破先生 : 実は興味を持っているのが、災害の時の食事についてです。日本は災害大国なので、災害発生時に、通常の食生活が止まってしまうかどうかは、すごく重大なことと考えています。また復興に向けては、やはり体が資本ですので、栄養を摂って、平穏な食生活をいかに保つかということも大切です。もちろん、食の備蓄に関しては、衛生管理にも関係します。
水分活性測定の重要性について
ー それでは、水分活性測定の重要性について教えてください。
不破先生 : まず給食の衛生管理という面で、HACCP対応はすごく重要です。私自身も日本食品保蔵科学会HACCP管理者の認定講師をしており、その重要性を感じています。
全ての製品を安全に市場に送り込むためには、製造現場で全件検査をする必要がありますが、これを非破壊で行うため、色々な測定方法を駆使することになります。
微生物を制御するためには、培養して検査すると結果が得られるまでに長く時間がかかるので、繁殖要因となる温度や水分活性等を測定して、その製品がどのような状況であるかを確認することが大切です。
このことは普段の講義でもよく話しており、実際に市場に出回っている製品がどのくらいの水分活性値なのか、講義で測定して見てもらい、その結果としてどのくらいの賞味期限となるのか、というように教えることもあります。

AwViewを導入された経緯について
ー AwViewを導入された経緯について教えてください。
不破先生 : 授業内で使用する測定器は、簡単で短時間に測定できるかが重要です。特に大学での授業では、1クラス40~50人程度となることもあり、効率的に教えるため小型で扱いやすいものを必要としていました。そんななか、別の大学の先生の紹介で、AwViewを知りました。
早速、AwViewを用意して、すでに所有していた他メーカーの水分活性測定装置との比較検証を行いました。というのもAwViewは簡単に水分活性の測定ができますが、実際の測定値は他の機種と同じような数値が出るのか、あるいは差があるのか、これを確認したかったからです。AwViewも含めて計3機種での検証を行い、生ハムや乾物、チーズ等の9つのサンプルを、それぞれ同時測定しました。その結果、どの機種も測定値に差がないことを確認できました。
AwViewは他の機種よりも非常に安価であるにも関わらず、遜色なく測定でき、かつスマホのアプリで簡単に測定できる点を評価し、授業に導入しました。学生はスマホを当たり前に持っていますので、アプリをインストールしてもらい、使用してもらっています。学生たちも、測定後すぐにアプリで測定結果やグラフを確認できる点を、使いやすいと感じているようです。

今回導入された水分活性測定器「AwView」
卒業発表におけるAwViewの活用について
ー 卒業発表のために、AwViewでの水分活性測定を実施されたと伺いました。卒業発表のテーマについて、教えていただけますか?
柴田様 : 先生からもお話があった災害時の食事について、災害時は食料調達の手段が限られてしまいます。特に道路が寸断されると、今持っているものしか食べることができません。備蓄品の目安は7日分と言われていますが、これを用意することはかなり大変だと思いました。
また災害の時に足りなくなる栄養は何か、ということを考えた時に、生鮮品である野菜が食べづらくなると考えました。停電によって冷蔵/冷凍庫で保存できなくなることが想定され、野菜を1日食べない程度では問題ないですが、その期間が長引くほど栄養面の問題が発生します。
野菜の缶詰もありますが、コーンやアスパラガス、グリーンピースくらいで、種類はあまり多くなく、かつ値段が高いです。そのため、あまり普及していないというのが現状です。
そこで、普段から家庭で食べている野菜を乾燥させて長期間、備蓄できるようにすることで、災害の時にも役立つのではないかと思い、家庭での野菜の乾燥方法を検討し、災害時の野菜の摂取量を増やすためのレシピ提案を目的とした研究をすることにしました。
ー 実際にどのようなことをされましたか?
柴田様 : にんじん、玉ねぎ、茄子の3つの野菜を、ドライフードメーカーで6時間乾燥させて、その衛生評価を目的にAwViewでの測定を実施しました。実際の測定は、乾燥前・乾燥直後・乾燥1週間後の3回行いました。乾燥後の値は、全ての野菜で0.5Aw未満となり、1週間後の値もほぼ変化がないことが確認できました。
また前処理の違いによる衛生面の影響も確認するため、生のまま乾燥・ゆでてから乾燥・塩をまぶしてから乾燥というように、パターンを分けて測定したところ、塩・生・ゆでの順に水分活性値は低く、前処理によって違いがあることが、今回分かりました。
これらの乾燥野菜を使って、パッククッキング(ビニール袋に食材を入れて、湯煎する調理方法)のレシピ提案を行いました。より多くのデータを集めレシピ提案を増やすことで、災害時の野菜摂取量増加に貢献できると考えています。




乾燥野菜を使用し、パッククッキングでつくられた料理
今後の取り組みについて
ー 最後に、今後の食品衛生に対する取り組みや、HACCPや水分活性に関わる測定器やメーカーに期待することがあれば、是非お話ください。
不破先生 : HACCPが制度化されてしばらく経ちましたが、まだ食品会社の皆様は色々と試行錯誤されている状況ではないかと思います。そのなかで、基礎データを集積することについて役に立てるならば、これからも関与していきたいと考えています。
その際に、難しい方法でしか測定できないということではなく、現場に即した測定が実施できれば、より食品衛生管理がスピードアップして、より良い方向に進むと思います。今後も誰にでも使いやすい測定機器が増えることを期待しています。
※本内容は2025年2月時点の情報に基づいています。
